「自分、けっこう英文スラスラ読めるかも?」
そう思ってたあの頃——TOEIC900を目の前にして、見事に打ち砕かれました(笑)
「英文をスラスラ読めるようになりたい!」
そう願う社会人は、全国に100万人はいるはず(トビー調べ)。
社会人になると、仕事やニュース、メールなど、なにかと英語に触れる機会は増えます。いまやAI翻訳も超優秀で、ほとんどの英文は正確に訳してくれる時代。
それでもやっぱり——生の英語を自分の頭で読める力を身につけたい。だって、そのほうがカッコいいし、何より書き手の本質がわかるから。
だから多くの人が「英文をスラスラ読めるように」と学び直しを始めるわけですが……。ここで、ふと湧いてくる素朴な疑問があるんです。
・「英文をスラスラ読める」って、どのくらいのレベル?
・TOEIC900? 英検1級? それともネイティブニュースが読めること?
これ、実はトビー自身がずっと感じてきたモヤモヤでした。
そして、英検1級&TOEIC900を取ったいまだからこそ、やっとわかったんです。——“スラスラ読解”の正体は、幻想だったと。
今回はそんなトビーが、言語オタクらしく(笑)この「スラスラの謎」に、独断と偏見たっぷりで迫っていきたいと思います。
・英検1級/TOEIC900レベルの「読解力」はどこまで通用するのか
・“スラスラ読める”が実は存在しない理由
・トビーが見つけた「心地よく読める=快読ゾーン」の定義
・今日からできる“スラスラ読解”への現実的ステップ
英検1級/TOEIC900の“読解力”はどこまで?|スラスラ読める境界線
トビーはこれまで、「TOEIC900」「英検1級」と、いわゆる“上級者ゾーン”まで走ってきました。——でもここで正直に言います。
英検1級でも、全部スラスラなんて読めません。
いや、むしろ「スラスラ」なんて単語、上級者ほど口にしなくなります(笑)
英検1級/TOEIC900の実力を客観的に見てみる
そもそも同じ英検1級でもスコアに幅があるし、TOEICでも900点の人と999点の人では天と地ほど差があるもの。
まずは、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に基づいた客観的な指標を見てみましょう。
| レベル | TOEIC換算 | 英検換算 | CEFR対応 | 読解レベル(客観的) |
| 中上級 | TOEIC 800〜 | 英検準1級 | B2 | 日常・ビジネス文書を理解できる(部分的に要辞書) |
| 上級 | TOEIC 900〜 | 英検1級 | C1 | 抽象的・専門的トピックも内容把握できる(時間をかければ精読可能) |
| 最上級 | TOEIC 950+ | 英検1級合格+α | C2 | 複雑な論文・学術テキストも即理解可能(母語並み処理速度) |
つまり、英検1級/TOEIC900=CEFR C1レベル。
この段階では「内容理解に問題はない」が、背景知識の差によって読解の深さが変わる。それは、トビーの体感としてもかなり的を射ています。
英検1級/TOEIC900=CEFR C1レベル|トビーの実感
客観的な基準がわかったところで、今度はトビーの実感と照らし合わせてみましょう。
・TOEICの文章は文法的にもほぼ読解できている(はず)
・英検1級の長文も、時間をかければ精確に理解可能(きっと)
・ニュースサイト(BBC/CNN)の一般記事は、語彙も構文もだいたい対応可能
・専門的トピック(トビーの場合は精密機器)の論文も時間をかければ精読可能
ちなみに2024年時点でのトビーの実力は実力はこんな感じ:
・英検1級:CEFR C1
・TOEIC:915点
つまり、自分の読解実力はまさにC1相当だったと、今になって納得しました(笑)
まとめると、英検1級/TOEIC900レベルは、ほとんどの英文を読めるけれど、ジャンルによって理解のムラが出る。これが「スラスラ読める」と「完全に理解できる」の分かれ目です。
心理言語学的にはこうなる|「読める」と「理解できる」は別物
心理言語学の研究でも、Reading=Decoding(解読)+Comprehension(理解) の掛け算で成り立っています。
上級者でも「Decoding」は速いけど、「Comprehension」は背景知識に左右される。
たとえば:
・国際関係や時事記事(War, Diplomacy, Global Affairs)
→毎日BBCを読んでいるので、トビーもわりとスラスラ。
・生命科学や哲学系(Genome Editing, Existentialism)
→普段触れない分野。頭の中が英語以前に混乱(笑)
つまり、「スラスラ読めるかどうか」は語学力だけでなく、背景知識×関心分野の掛け算で決まるんです。
まとめると、英検1級やTOEIC900というのは、「英語を読む力」のゴールではなく、ようやく“読むための土台が完成した段階”なんです。
ここが、ほんとうの意味での「スラスラ読める境界線」。
この先にあるのは、速さではなく、理解の深さを楽しめる世界です。

「まじかっ?」って思われるかもしれませんが、
英検1級/TOEIC900を超えてからの方が、英語が本気で面白くなります。スラスラじゃなく“じっくり味わう”ほうが、圧倒的に楽しいんです。
“スラスラ神話”は存在しない|主観がつくる読解の錯覚と限界
すでに冒頭でも言ってしまいましたが──
はい、残念ながら“スラスラ”なんて、客観的に存在しません。
英語学習者が夢見る「スラスラ読めるようになりたい」は、言ってしまえば主観的な体感であって、測定できるスキルではないんです。
「速く読めた」は危険信号|“上滑り現象”という理解の錯覚
みなさんも、こんな経験ありませんか?
TOEICで時間に追われ、必死に速読しているつもりなのに──
理解が追いつかず、目が英文の上をただ滑っていく。
結果、スコアは惨憺たるもの。
この怪奇現象、トビーはリーディングの「上滑り現象」と読んでいます。特にTOEICのPart7で出没しがち(笑)。
本人は「スラスラ読めた」と思っていても、最終的に内容を説明できないのなら、それは“理解の錯覚”です。
つまり、「読む速さ=理解の深さ」ではない。
本当に大切なのは、内容を正確に理解できているかどうかなのです。
テキスト難度×自分の実力|“適正レベル”で左右される理解の度合い
もうひとつ、忘れてはいけない要素があります。
それは、「読む英文の難易度」と「自分の英語力」がどれだけマッチしているか。
たとえば、英検2級やTOEIC700の人が、いきなりBBCニュースを読んでも、“スラスラ”の“ス”にも届かないかもしれません。語彙も文構造も複雑すぎて、頭が追いつかないのは当然です。
でも同じレベルの人が、中学生向けのリーディング教材を読んだら──
きっと気持ちよく読めるでしょう。
つまり、スラスラ感は「難度のマッチング」で生まれる錯覚なんです。
実際、トビーがBBCやCNNの国際面(外交・戦争・時事ニュース)を
頻繁に読むようになったのは、TOEIC900超/英検1級をクリアしてから。
このレベルになると、語彙と構文の土台があるため、あとは「慣れ」の問題で、かなり心地よく読めるようになります。
“快読ゾーン”の方程式|背景知識×語彙力×構文力
では、英文の難易度と読者の読解力が適正に噛み合っているとき、
「読みやすさ」を決めているのは何でしょうか?
トビー的には、この3つのバランスです👇
1. 背景知識(Content Knowledge)
文の意味を“推測”する力。これが最も大きな要素。
2. 語彙力(Vocabulary Coverage)
未知語が2%以下になると、リーディング理解率は急上昇(Nation, 2001)。
3. 構文力(Syntactic Parsing)
SVOC・修飾関係を即座に把握できる力。これは精読で鍛えられる部分。
この3つがそろった瞬間、英文は一気に“読める”ようになります。
そして、その状態こそが──トビーが呼ぶ「快読ゾーン」です。

「スラスラ」とは“読む速度”じゃなくて“理解が途切れない心地よさ”のこと。では次の章から、英文を心地よく読むための具体条件を深掘りしていこう。
英文を“心地よく読める”条件とは|トビー的・快読ゾーンの定義
「スラスラ読める」という幻想を捨てたあとに残るのは、
“心地よく読める”という、もっと現実的でポジティブなゴールです。
これは「理解の途切れない心地よさ」と「読めているという安心感」が重なったときに訪れます。トビー的に言えば、まさに“快読ゾーン”。
では、その“快読ゾーン”に入るための条件を見ていきましょう。
2段階下がちょうどいい|「理解の余裕」が生む心地よさ
トビーがBBCやCNNを読んでいて感じるのは、「自分のレベルより2段階くらい下の英文」を読むときが、いちばん心地よいということ。
TOEIC915点・英検1級のトビーにとっては、たとえばCEFRでいえばB2レベル、つまり英検準1級〜TOEIC800台くらいの英文がそれにあたります。
このレベルなら、
・9割以上の単語が既知語
・構文も自然に目で追える
・戻り読みゼロでも意味が取れる
・文章から情景が浮かんでくる
──そんな“安心感と没入感”の両立が生まれるんです。
要するに、「少し余裕のあるレベル」で読むことが、読む快感を最大化するコツ。
難しすぎる文章を“筋トレ”的に読むより、「ちょっと簡単」「内容がわかる」文章を大量に読むほうが、結果的に理解力もスピードも伸びます。
科学的にも証明されている“快読の条件”
実はこの「心地よく読めるゾーン」、
第二言語習得研究でも明確なデータがあります。
・未知語率が約2%以下(既知語98%以上)になると、理解率が急上昇する。(Nation, 2001)
・理解可能なインプット仮説(i+1)でも、“ほんの少しだけ難しい内容”こそが最適な学習刺激になるとされています。
つまり、「8〜9割理解以上できる英文」が“退屈すぎず、難しすぎない”理想的なライン。ここにこそ、“快読ゾーン”の科学的裏付けがあるんです。
トビー的・快読ゾーンの定義
ではでは、トビーが考える“快読ゾーン”を改めて整理してみましょう👇
①方程式:「背景知識×語彙力×構文力」が揃っている。
②自分のレベルより2段階下の英文を読む。
③戻り読みせず、英語を英語のまま理解できる。
これが揃ったとき、人は“ゾーンに入る”。
いわゆる「読んでる自分を忘れる状態」です。
読者ドン引き覚悟で言語オタクのトビーから言わせてもらえば、言葉というのは発信者の意図(=言いたいこと)をルールに沿って暗号化したものなんです。
そのルールとは、使う言語そのもの──つまり単語と文法。
英文を読むことは、その暗号を解読(デコード)して、発信者の意図を正確に再構築することに他なりません。
英語→日本語に置き換える翻訳を介すると、どうしてもこの“脱暗号化”の精度が落ちてしまう。だからこそ、「英語を英語のまま理解する」=本物のデコードが必要なのです。
この領域に入った瞬間、
アルファベットがそのまま意味として浮かび上がってくる──
そう、ここが「快読ゾーン」。エクスタシ〜(笑)
そしてその瞬間、
「読む」ことはただの作業ではなく、知的快感そのものになるんです。
(変態ではないです、たぶん笑)
英文を「心地よく読める」ようになるには|トビー流・地に足ついた読解メソッド
“快読ゾーン”に入るには、
魔法のようなテクニックも、派手な裏ワザもありません。
……え、ガッカリしました?(笑)
はい、先に謝っておきます。トビー式は地味です。
でも、地味こそ正義。
必要なのは「確実に効く基礎トレーニング」。
必要なのは、地味だけど確実に効く基礎トレーニング。
トビーが実際にやってきて、「これだけは外せない」と思った5つの習慣を紹介します。
①「精読/構文読解」がマスト!|文法は読解の地図
「文法キラ〜イ、ナニソレ〜」って目をそらしたくなる気持ち、わかります。
トビーも通ってきた道です(20年越しで実感)。
文法はホントにめんどい。
でもですね。
上級レベルの快読ゾーン目指すのなら、基礎文法と構文読解からは「絶対←フォント100で」に逃れられません(きっぱり)。
いえいえ、「ロイヤル英文法を5回読め」なんて言いません。
でも、文法を“避けない覚悟”は持ってください。
文法は“英語の地図”です。地図なしではどんなに頑張っても遭難します。
関連記事(基礎文法編):
→「あなたは感覚派?ガチ文法派?|英検1級/TOEIC900が厳選した英語参考書おすすめ10選」
→「基礎文法はどこまで?|文法沼にハマってはいけない3つの理由」
関連記事(精読編):
→「基本はここだ!」は本当に効く?|精読の壁を突破する“最初の一冊”の使い倒し術」
→「ポレポレはこう使え!英検1級/TOEIC900が教える最強精読本完全攻略」
②単語は“量”を“定着”させる|覚えて、使える状態に
“心地よく読む”ためには、語彙力は欠かせません。
でも、やみくもに単語帳をめくるだけではダメなんです。
トビーが10,000語以上を覚えられたのは、
「書かずに覚える」+「何度も出会い直す」スタイルだったから。
つまり、
・単語帳で見た → 忘れる
・実際の英文で出会う → 思い出す
・何度も出会う → 定着する
この“再会のサイクル”こそが記憶を深く刻む。
単語は「暗記するもの」ではなく、「再会して馴染ませるもの」。
この感覚が身につくと、語彙が“使える英語”に変わります。
関連記事:
→「英単語は「書かないで覚える」はアリ?|TOEIC900・英検1級を超えた記憶術の真実」
→「英単語は走って覚える!?|トビー式“忘れない記憶”の五感暗記術とは?」
→「単語帳の選び方、結局どれが最強?|TOEIC・英検対応タイプ別おすすめ戦略を解説!」
③「日本語訳」と対にして読む|“わかったつもり”を避ける
これは意外と見落とされがち。
正しい日本語訳とセットで読むのは、理解の精度を上げる最高の方法です。
トビーも以前、「なんとなくわかった気がする英文」を山ほど読み流していました。でも、あとで模範訳を見ると「全然ちがう!」。
ニュアンスだけで読んでいると、
自分の中で“意味を都合よく補完”してしまうんです。
まずは一度、信頼できる訳で正確な意味を確認し、そのうえで「英語のまま理解できるまで」何度も読む。これが「読めたつもり」を防ぐ最短ルートです。
関連記事:
→「“読めてるつもり”が英語を止めてた|20年迷走したトビーが見つけた精読の力」
④理解できた英文を“反復リーディング”する
一度理解できた英文は、宝です。
その一文を、何度も読む。音読する。タイピングする。
トビーもTOEICや英検の勉強中、覚えるほど何度も反復リーディングしました。
繰り返すほど、
・語彙が自動化する
・構文がパターン化される
・読解リズムが整う
結果、英文を読んでいても「日本語に変換しないで意味が浮かぶ」ようになります。この感覚が、“快読ゾーン”の本質なんです。
⑤多読はゴール|でも“単語+精読”が先
最後に、これを言わせてください。
多読は素晴らしい。でも、順番を間違えると挫折します。
トビーも昔、多読にハマってBBCの記事を読みまくったことがあります。
でも、精読が足りないうちは「量だけこなして理解は浅い」状態。
だからこそ、最初に「精読」と「単語」を固めてから多読に進む。
基礎ができたあとに読む英文は、まるで景色が変わります。
多読は“筋トレ”ではなく、“旅”です。
読めるようになったあとで読むからこそ、楽しく続けられるんです。
関連記事:
→「TOEIC・英検に“多読”は必要か?|900点突破のカギは「精読→多読」の正しい順番だった!」
→「英文多読、なに読めばいい?|精読マスター後に使える“英文ニュースサイト”活用術」
まとめ|“スラスラ”より“じっくり”が最短ルート

ここまで言語オタクの長文記事を読んでくださり、本当にありがとうございます。
この記事のタイトルにもあるとおり、
“スラスラ読めるようになりたい”という願いは、英語学習者の永遠のテーマですよね。
でも、その切実な願いを──
トビーは冒頭であっさり一刀両断してしまいました。
「スラスラなんて幻想はないよ〜」と。
でも、これは真実です。
言語の勉強に近道や特効薬はありません。
みなさんも日本語を使いこなせるようになるまで、
何年もかけて言葉のシャワーを浴びてきたはずです。
それと同じで、英語も時間をかけて少しずつ“読める脳”を育てるしかない。
それが自然で、いちばん確実な方法なんです。
外国語というのは、そもそも「未知の世界の窓を、別のルールでのぞく作業」。
いろんなジャンルの文章を「そこそこ」読めるようになるまでだって、想像以上に時間がかかります。
だからこそ、
“スラスラ”より“じっくり”が最短ルート。
単語も、文法も、精読も、コツコツ積み上げたうえでの多読こそ、
“快読ゾーン”への正しい道筋です。
時間はかかります。
でも、「正しい努力」の積み重ねは決してあなたを裏切りません。
このブログのどこかに、
英語学習のヒントや小さな気づきを見つけてもらえたらうれしいです。
そしていつか、
「快読ゾーン」でお会いできる日を楽しみにしています 。
このブログを書いた人:トビー
20年迷走して、ようやく“精読の壁”を超えた人です(笑)
トビーって何者?って思った方は、こちらをどうぞ(笑)
→このブログについて|20年迷走して気づいた“精読”の力とTOEIC900の壁

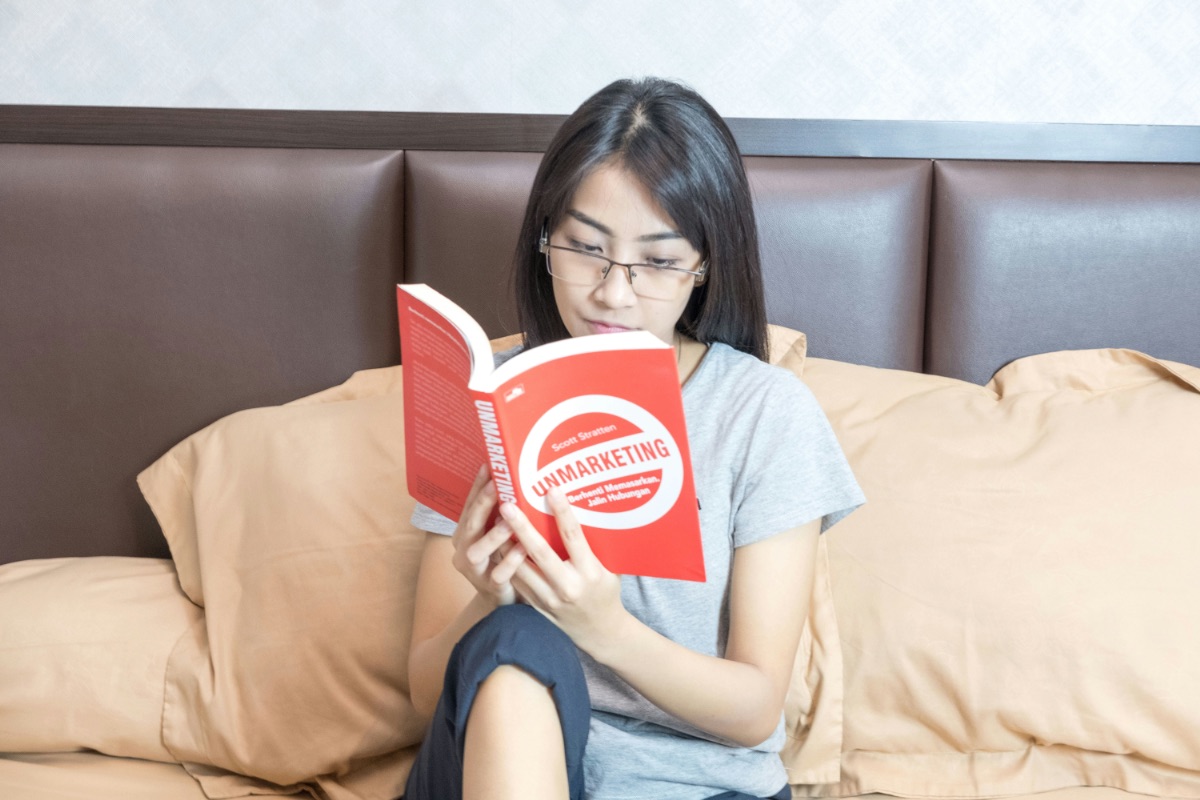



コメント