拝啓:公益財団法人 英語検定協会さま。
2024年度の試験改訂、本当にありがとうございました。
……おかげさまで、受験生みんな地獄を見ました(笑)。
改訂後に突如として現れた「要約問題」。
問題文にはこう書いてあります:
Read the article below and summarize it in your own words as far as possible in English.
(下の記事を読み、できる限り自分の言葉で英語にまとめなさい。)
──“できる限り自分の言葉で”って…
某国の政治家の答弁みたいに、定義あいまいすぎ(笑)
従来は小論文一本勝負で、テンプレを叩き込めばある程度突破できた。
でも今回からは「基準が見えない新問題」が登場し、受験者は混乱。
「採点どうなる?」「対策本ないし…」と全国がザワついた、はず。
・英検1級「要約問題」の出題形式と狙い
・過去問から見える典型パターン
・合格点を狙える“4文フォーマット”
・トビーの迷走と最後にたどり着いた方法論
今回の記事では、そんな要約問題に対して、
トビーがどう立ち向かい、どう攻略して合格までこぎつけたかを、
ユーモアと(少々の恨み節)を交えて語っていきます。
要約問題ってどんな試験?|出題形式と狙いを整理
2024年度の改訂で新登場した「要約問題」。
実は英検1級だけでなく、準1級・2級・準2級・3級にも導入されました。
つまり英検はこれから、“読むだけ・書くだけ”ではなく、
読んだ内容を整理して、自分の言葉でまとめる力を測ろうとしているのです。
英検1級のライティング配分はこう変わった
・試験時間:100分
・ライティング:50分(約半分!)
- エッセイ(25分)
- 要約(25分)
これまでは「小論文1本勝負」でしたが、
今は “エッセイ+要約”の二刀流を要求されます。
──協会の公式な狙いは?
英検協会の発表によれば:
「新たな英語能力観を反映した主題形式を取り入れた新問題」
うーん、公式文もなかなか抽象的(笑)。
要するに、「英語を書く力」をもっと多面的に測ろう、ということ。
小論文はパターン暗記で突破されやすい。
そこで、“即興力”や“要点抽出力”が問われる要約を追加したのではないか、というのがトビーの推測です。
──採点は甘い? 厳しい?
受験者の声をまとめると──
・採点はやや甘め?
・内容が少しズレても、構成と文法が整っていれば点はもらえる
・ただし基準が不透明で、合否の境目が読みにくい
改善か、改悪か。ここは意見が真っ二つに分かれるポイントです。
英検1級小論文の攻略法はこちらの記事をどうぞ:
→英検1級 小論文はこう超えた|“写経×ChatGPT”で型を覚えて最短合格!
トビーの体験談|迷走から“方法論”との出会いまで
最初の印象|文章はやさしいのに要約はムズい!
英検1級の公式サイトに出ていた出題例を見たときの第一印象は──
「文章自体はやさしい。単語もシンプルだし、読みやすいな」でした。
ところが落とし穴がここ。
“全文を理解したうえで、自分の言葉で90〜110語にまとめる” という制限がある。
つまり「読解→抽象化→圧縮」を一気にやらなければならず、これが想像以上に難しかったのです。
市販の問題集に挑むも不完全燃焼
まずは『英検合格のための要約問題予想問題集』を購入。
良かったのは、模範解答に加えて「モニター回答(一般受験者の解答)」が載っていたこと。「どこが良くて、どこがダメか」を客観的に見比べられるのは大きな学びでした。
ただ──残念なのは、「どんな問題にも通用する要約の手順」が書かれていなかったこと。
さらに本番の出題形式とも微妙にズレており、対策としては「惜しい」内容でした。
1ヶ月かけても自信ゼロの迷走期
トビーは一次試験に向けて約4ヶ月勉強。そのうち 1ヶ月を要約問題に集中投下しました。
でも結果は、自信がゼロに近い状態(笑)
「これ本当に点数になるの?」という不安だけが募り、どんどん迷走に。
救いの神はYouTube「Wataru」さん
試験直前、たまたまYouTubeで英語講師「Wataru」さんの要約解説動画を発見。
ここで初めて知ったのが、“どんな英文にも共通する要約の型”でした。
・段落ごとの要点を抽出
・全体の論理展開を見極める
・定型フォーマットに落とし込む
この「方法論」に出会った瞬間、霧が一気に晴れた感覚!
試験前の最後の1週間は、この動画のリピート視聴で仕上げに成功しました。
英語が上手く書けないのは語学に向いていないせい? 気になる方はこちらの記事をどうぞ:
→語学が“向いてる人・向いてない人”の違いとは?|英検1級&HSK6級トリリンガルが徹底解説
出題のパターンを知れ!|過去問から見える共通構成
要約問題を解くうえで最重要ポイントは、英文の“型”を見抜くことです。
実は過去問を読み込むと、出題文にはほぼ共通する「お約束の流れ」が存在します。
英検1級の要約文は“三段構成”だった!
これまでの過去問を分析すると、多くの文章が次のような三段構成になっていました。
第一節:テーマの説明(モノ・コト・現象の紹介)
第二節:問題点とその影響(課題が社会や個人に与えるインパクト)
第三節:対策と残された課題(解決策+まだ残るハードル)
つまり、与えられた文章は「テーマ紹介→問題提起→解決策」という論理展開で流れることが多いんです。
この型を押さえておけば、「あ、今は第2段落=問題点を言ってるな」と位置づけができ、要約作業がグッとラクになります。

過去問題を読んで「パターン慣れ」しておくことが大切ですよ。ほぼ同じフォーマットで構成されているのに気が付くはずです。
対策本より“過去問精読”が効く理由
もちろん、市販の参考書や予想問題集も役立ちます。
ただ、実際の本試験と微妙に形式が違うケースも多いんです。
トビーも最初は予想問題集を回していましたが、本番形式とズレていたせいで「かなり」混乱しました。
最終的に一番効果があったのは、過去問を徹底的に精読して型を体に染み込ませることでした。
「型」を知ると、迷子にならない
試験本番は時間との戦いです。
要約の流れを頭に入れておけば、文章を読みながら「ここが第1文、ここが第2文…」と自然に整理できる。
逆に型を知らないまま臨むと、情報に振り回され、どこを削ってどこを残すか判断できずに沈没します。
要約問題を突破するには、まず 「出題の型=三段構成」 を自分の地図にしておくこと。これが、攻略の第一歩です。
英検1級2次試験対策の記事はこちらからぞうぞ:
→英検1級2次試験はこうやって切り抜けた!|時間ゼロでも合格できたトビー流 面接攻略法
要約の方法論|4文でまとめる“鉄板フォーマット”
要約問題の一番のハードルは、「理解した内容を90〜110語に収めること」です。
ここで便利なのが、どんな問題にも使える “4文フォーマット”。
本文の三段構成(テーマ → 問題点 → 解決策)を、4文に圧縮して表現する方法です。実際に英検公式サイトの模範解答も、この4文フォーマットに近い形になっています。
まずは全体像|4文フォーマットの黄金ルール
第1文:テーマの紹介(本文第1節の要点をまとめる)
第2文:問題点とその影響(本文第2節の要点を1文で)
第3文:提示された対策(本文第3節の「解決策」部分)
第4文:残された課題(本文第3節の「限界や問題点」部分)
この順番に沿えば、本文の全体像を漏れなく整理でき、語数も自動的に90〜110語に収まります。

これ以降は、英検1級2025年第1回の要約問題をベースに解説していきます。問題文は公式サイトからダウンロードして確認してみてくださいね。
第1文|テーマを抽象化して客観的にまとめる
英検1級2025年第1回のテーマは「The Ogallala Aquifer」(オガララ帯水層)。
ここで注意すべきは、本文が「帯水層全般」ではなく、特定のオガララ帯水層について述べていることです。
テーマの範囲を誤ると、その後の要約全体がズレてしまいます。
本文第1節では次の2点が述べられています。
①オガララ帯水層は地域経済に不可欠
②農業・飲料水・その他多方面に利用されている
模範解答の第1文は、この内容を抽象化して一文にまとめています:
The large volume of water extracted from the Ogallala Aquifer is the bedrock of the region’s agriculture industry.

aquifierなんでマニアックな単語を知らない人でも大丈夫。本文では「an underground layer of rock 」と説明がされています。
第2文|問題点とその影響を原因・結果で表す
第2文は「問題点」と「その影響」を原因と結果の関係でまとめます。
本文第2節では:
①問題:地下水の過剰な汲み上げで水位が下がっている
②影響:
1)農産物の輸出減少 → 地域経済への悪影響
2)世界的な食糧価格の高騰リスク
模範解答はこう表現しています:
This makes it alarming that over-extraction of water from the aquifer could eventually lead to diminished agricultural production, potentially inflating food prices across the globe.
👉 使える定型フレーズ
・This has resulted in problems such as…
・However, it causes several issues including…
・As a result, … has become a serious concern.
第3文|本文の解決策を1文で整理する
第3文では、本文で紹介された「解決策」を一文にまとめます。
第三段落前半に、上記の問題を受けての「対策」が述べられているのでピックアップしましょう。
本文第3節の前半では:
・一部の州で取水制限を導入
・農家に水量計の設置を義務化
模範解答:
To head off this looming crisis, local governments are restricting water extraction from the aquifer that can be used for agriculture through regulations and compulsory monitoring of water consumption.
👉ここでも定型フレーズが使いやすいです。
・To address/tackle these issues, …
・One proposed solution is to…
・In response, …
留学しないと英検1級はムリ?そんなことないですよ。気になる方はこちらから:
→英語は留学なしで伸ばせる?|純ジャパのTOEIC915&英検1級“国内完結”戦略
第4文|逆説表現で“残された課題”を示す
最後は「課題や限界」で締めます。
本文第3節の後半にあたる部分を拾えばOKです。
ポイントはhoweverなどの逆説を展開するディスコースマーカー。
これが第三段落に出てきたら「これが課題だな」と検討をつけることができます。
本文に挙げられている課題:
・水量計の設置コストが収益を圧迫
・取水制限による不動産価格の下落
・農業継続そのものへの懸念
模範解答:
Despite the plan’s benefits, the mandates regarding the aquifer pose serious economic threats that could doom local farmers’ businesses.
ここでのお決まりのフレーズは下記の通りです。
・Unfortunately, ….
・Nevertheless, …
・Despite… , …
まとめ|4文フォーマットの完成形
第1文:テーマを客観的に述べる
第2文:問題点+影響を原因・結果で表す
第3文:解決策を本文からピックアップ
第4文:逆説表現で課題を残して締める
この流れを“型”として覚えておけば、初見の問題でも迷わず90〜110語で要約できます。
TOEIC、英検、高得点取って良かったことのホンネ語ってます。こちらからどうぞ:
→TOEIC900点・英検1級、取ってよかった?|達成後に気づいた「本当の価値」と反省点
まとめ|要約問題は“型”と“理解力”で突破できる!

ここまで、英検1級の新設「要約問題」について整理してきました。
結論を一言でまとめるなら:
👉 「出題の型」と「4文フォーマット」を押さえれば、合格点は十分狙える!
要約問題は、いわば「精読力+圧縮力」のテスト。
小論文のようにオリジナルの意見を展開する必要はありません。
本文を正しく理解し、それを自分の言葉で90〜110語にまとめればOK。
「自分の言葉で」と言われると身構えてしまいますが、
要は「本文の流れを正しく整理して英語に直すだけ」なんですよね。
次のステップとしては、この記事で紹介した「4文フォーマット」を使って、まずは過去問1題を実際に解いてみましょう!
この記事が、要約問題に悩む子羊さんたちの指針になれば幸いです🐑。
このブログを書いた人:トビー
20年迷走して、ようやく“精読の壁”を超えた人です(笑)
トビーって何者?って思った方は、こちらをどうぞ(笑)
→このブログについて|20年迷走して気づいた“精読”の力とTOEIC900の壁

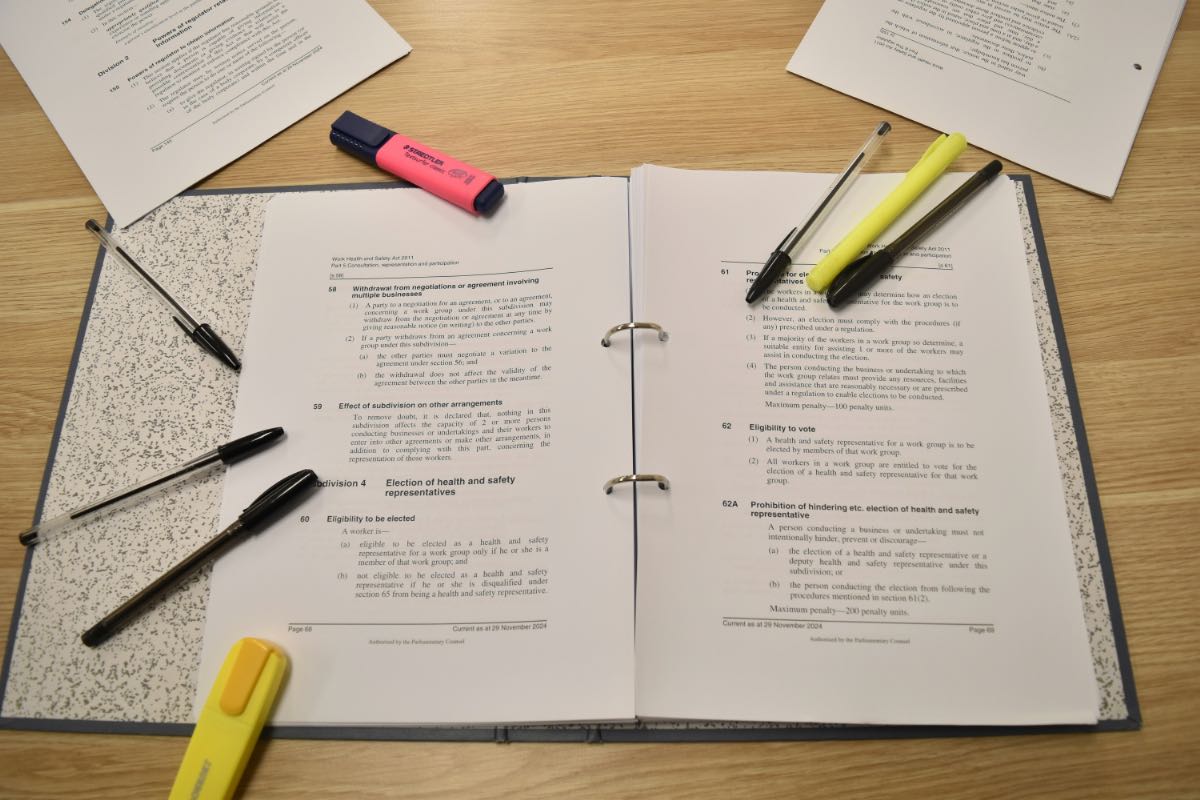



コメント