電車の中で英文ニュースをさらっと読んでる人。
カフェで分厚い洋書をパラパラめくってる人。
──正直、みんな敵だと思ってました(笑)
基礎文法はやったはずなのに、長文になると全然理解できない。
単語はわかるのに、意味がつながらない。
これ、全国100万人の英語学習者がぶつかる「英語長文読解の壁」です。
安心してください。あなただけじゃありません。
でもですね──
英検1級・TOEIC900・HSK6級を取ったトビーに、ちょっとマウント取り気味に言わせてください(笑)。
👉 英語って、本当は日本語や中国語よりずっとシンプルな言語なんです。
コツさえつかめば、「拍子抜けするくらいシステマティック」に読めるようになる。それなのに多くの日本人が苦しむのは、日本語と英語で“言語のシステム”がまったく違うからです。
トビーは学者じゃありません。
でも20年以上の迷走と失敗を経て、「英語はもっとシンプルに読める」という事実に気づきました。
今回はそのコツを、体験談ベースでまとめてみました!
・英検1級保持者の「英語長文の読み方」 ─ じつはSVOCと修飾語しか見ていない⁉
・本当に必要な文法知識 ─ 文型と修飾語の理解で長文はシンプルになる
・BBCニュースで実践! 英文を「構造」で読むトビー式の読み方
・なぜ日本人は長文が苦しいのか? 日本語との“言語システムの違い”から解説
英検1級保持者の「英語長文の見方」──学べば学ぶほどシンプルになる
英語長文を読むとき、トビーが意識しているのはたったひとつ。
「これはSVOCのどれ? そして修飾語はどこにかかってる?」
英検1級も、TOEICの長文も、BBCやCNNやFox Newsも、みーんなこれだけ。
逆に言うと、この2点がわからなければ、どんなに単語を知っていても絶対に正しく読めません。でもSVOCと修飾語さえ見抜ければ、英文は一気にシンプルに整理できるんです。
英語は実はシンプルなんだよ、ってことわかってもらうために他の言語とも比較してみたいと思います。
・日本語:格助詞(てにをは)が豊富すぎて、語順が自由。そのぶん構造は複雑。
・中国語:文法はシンプルだけど、語彙が爆発的に多い。意味の幅が広すぎて一筋縄ではいかない。
・英語:語順と修飾語の位置で意味が決まる。つまり「構造」をつかめば、文はむしろ単純。

仕事で英語も中国語も使っていますが、英語の方がシンプルで翻訳もしやすいです。
じゃあなぜ英語が難しいと感じる人がこんなに多いのか?
多くの学習者がつまずくのは、この 修飾語の見極め です。
前にかかるのか、後ろにかかるのか。
どこまでが主語で、どこからが形容詞節なのか。
トビーも20年以上の迷走で、これには本当に苦労しました(涙)
でもこの判断があいまいだと、意味がつながらず「長文が読めない地獄」に突入します。
💡 結論:
・英語長文=SVOC+修飾語のパズル。
・単語力や感覚ではなく、構造を見抜く目を持つことが“シンプルに読める第一歩”なんです。
迷走して見つけた精読の大切さ。「SVOC+修飾語のパズル」を解くのにはこの記事も役に立ちます。
→“読めてるつもり”が英語を止めてた|20年迷走したトビーが見つけた精読の力
本当に必要な文法とは?
「英語長文を読むには、どこまで文法を勉強すればいいの?」
って素朴な問いには、「基礎文法はどこまで?|文法沼にハマってはいけない3つの理由」で詳しく書きました。
でも正直、多くの学習者がここで迷子になっていると思います。
みなさんは学生の時から、関係代名詞やら過去完了やら、たくさんの文法を学んできたはずです。でも、それらすべてをこと細かく勉強し尽くそうとすると、いくら時間があっても足りません。
実は、長文読解においてトビーが本当に必要だと思うのは、この3つだけです。
1. 品詞を見抜く力(SVOCの土台)
👉 主語・動詞・目的語・補語を見極められることが最優先。
2. 文型(5文型)の知識(骨格をつかむ)
👉 実際の英文は、この5文型の応用でしかありません。
3. 修飾語の理解(前にかかるか?後ろにかかるか?)
👉 文法書では独立した章が少ないですが、読解では最重要。これが見抜けないと意味が崩壊します。
「分詞の限定用法と叙述用法」とか、「完了形の「継続」と「経験」と「完了」の意味の違い」とか、「態の転換による語順の変化」とか、「目的を表す副詞節を導く接続詞」とか、「原因・理由を示す前置詞」とか、「名詞の体系的分類」とか、「定冠詞の拡大用法」とか、「動名詞だけを目的語にとる動詞を覚えろ」だとかは…(と、分厚い文法書に恨み節たっぷりで)、
──英検1級でも問われません(笑)
ここで誤解してほしくないのは、トビーは「基礎文法なんて不要」と言っているわけではないということです。
むしろ、基礎文法は絶対に必要。でもそれは“文法マニアになるため”ではなく、「精読=構文読解」で使うための基礎体力なんです。
外国語は、正しく理解してナンボ。
文法を学ぶのは目的ではなく、読解という実戦のため。
だからこそ、先ほどの 3つ(品詞・文型・修飾語) は、英語長文を読む上で本当にエッセンシャルなんです。
正しく理解できれば英検1級だって夢じゃない。詳しくはこちらから:
英検1級はどう超えた?|迷走20年のトビーが“独学×AI”で突破した戦略
BBCで実践!シンプルな英文の見方
ここまで「SVOCと修飾語がわかれば英語はシンプルに読める」と話してきました。でも理屈だけではピンと来ませんよね。
そこで今回は、実際の英文を使って“シンプルに読む練習”をしてみましょう。
例文①「Black lives matter.」
世界的なスローガンにもなったこの1文。
実は、プロの翻訳者ですら誤訳したという逸話があります。
ちなみにトビーが初めてこの文を見たとき……
「Black life is matter.」あるいは「Black life’s matter」の誤記かな?」 と本気で思ってました(笑)。
でも実際には、これはとてもシンプルな SVの第一文型 。
訳は「黒人の命は重要である」=「黒人の命は大切だ」となります。
主語(S):Black lives
👉 「黒人の命」。不規則変化で life → lives になる点に注意。
動詞(V):matter
👉 「重要である/価値がある」という自動詞。
ではなぜ誤解しやすいのか?
1. “matter”を名詞で覚えている
👉 「問題」とか「事柄」の意味で暗記していて、「動詞=重要である」を知らない。トビーが「Black life is matter.」と勘違いしたのはまさにこれ。
2. “Black lives”が主語と見抜けない
👉 「matter」を動詞と認識できれば、「Black lives」が複数主語だとすぐわかる。
3. 第一文型が理解できていない
👉 「S+V」だけで文が完結することに違和感を持ちやすい。
でも「I eat.」「I go.」だって立派な英文。第一文型は英語の超基本パターンです。
さて、どうでしたでしょうか?
こんなにも短い例文でも、前回の章で触れた、
1. 品詞を見抜く力
2. 文型の知識
がなければ正しく読めません。
さて、ここまでで「第一文型を正しく読む」感覚がつかめたと思います。
次はもう少し複雑に、「3. 修飾語の理解」も絡めた例文に挑戦していきましょう!

簡単そうに思える英文でも奥が深い。読めるフリしてスルーしてしまうのが一番良くないですぞ。
例文②「This signals to the fact that …」
BBCの記事から少し長めの文を取り上げてみましょう。
「India can’t wish away coal – but can it be made cleaner?」というタイトルの記事からのピックアップです。
This signals to the fact that, realistically speaking, coal – albeit cleaner coal – may remain the primary power source of energy in India, despite years of international climate talks asking for the highly polluting fossil fuel to be phased out entirely.
BBCキタ!
情報多すぎで目が泳いでしまいませんか?
実際、文型を見抜けないと一瞬で意味をロストするタイプの英文です。
でも結果から言うと──
👉 This signals.
S(主語)= This
V(動詞)= signals
つまり骨格は 第一文型(S+V)。
「This signals = これは示している」──たったこれだけです。
ではそれ以外は?ってことですが、「全部修飾語」なんです。
・to the fact that 以下:示している「内容」
・realistically speaking:副詞句(「現実的に言えば」)
・coal – albeit cleaner coal –:挿入句(「石炭、それも“よりクリーンな石炭”であっても」)
・may remain … in India:主要な内容(「インドでは主要なエネルギー源として残るかもしれない」)
・despite years of …:譲歩(「国際的な気候会議で廃止を求められてきたにもかかわらず」)
読みずら〜い!ってクレームが来そうですが、そうしている理由はこんな感じでしょうか?
難しいポイントまとめ
1. 情報の挿入が多い
👉 ダッシュやカンマで次々に追加情報が挟まれる。
2. 本動詞が見えにくい
👉 “signals” が修飾に埋もれて見つけにくい。
👉 今回は「自動詞=示す」として使われています。
3. 修飾語が見抜けない
👉 どこが飾りで、どこが骨格かを判断できないと文意が迷子に。

この「signal」が他動詞ならばsignal + O(= Oを示す)として使われるはずです。しかしここでは signal + to + O となっています。これは「目的語」ではなく 前置詞 to を伴った自動詞的な用法 です。
ちなみに、直訳(構造を残した訳)はこんな感じです。
これは次の事実を示している:
現実的に言えば、石炭――よりクリーンな石炭であったとしても――は、国際的な気候会議が何年も「その汚染度の高い化石燃料を完全に廃止せよ」と求めてきたにもかかわらず、インドでは主要なエネルギー源として残り続けるかもしれない。
今回は「ひっかかりやすい」BBC英文をあえて取り上げました。
でも大丈夫。こういう文も「シンプルな読み方」で攻略できます。
さあ、めげずに次の例文に進んでみましょう!
この記事読んだらマニア決定(笑)。BBCとCNNの違いはこちらから:
→BBCとCNN、どっちが読みやすい?|読者目線で分かった“英文ニュース”の選び方
例文③「For the president to do this … is only going to incite …」
BBCの記事からもうひとつ、読解のハードルが高い文を取り上げます。
記事のタイトルは「Trump’s intervention in LA is a political fight he is eager to have」です。
“For the president to do this when it wasn’t requested, breaking with generations of tradition, is only going to incite the situation and make things worse,” said New Jersey Senator Cory Booker.
さあ、どうでしょうか?
いきなり For から始まっているし、途中でカンマが入っているし、どこがどうなってるの〜?って悲鳴が聞こえてきそうです(笑)
でも結果から言うと、この文は 「I am a student」と同じ第二文型(SVC)。
骨格を分解してみましょう。
S(主語)= For the president to do this
👉 「大統領がこれを行うこと」=to不定詞句全体が主語。
V(動詞)= is
👉 be動詞。
C(補語)= only going to incite the situation and make things worse
👉 「事態をあおるだけで、もっと悪化させるだろう」=be動詞の補語部分。
それ以外は全部修飾語です。
修飾・挿入要素
・when it wasn’t requested:副詞節(「要請されていなかった時に」)
・breaking with generations of tradition:分詞句(「何世代にもわたる伝統を破って」)
これらが主語部分(For the president to do this)に挟み込まれていて、文を複雑に見せています。
難しいポイントまとめ
1. 主語が to不定詞句
👉 「For + 人 + to ~」は英語長文の定番主語パターン。
👉 「For + 人」はto不定詞の形式上の主語。
2. is の補語が長い
👉 「only going to incite … and make …」がズラズラ続く。
3. 挿入要素が邪魔する
👉 when節や分詞句が入って、SVCの骨格が見えづらくなる。
直訳はこんな感じです:
「要請もされていないのに大統領がこれを行うことは、
長年の伝統を破る行為であり、
事態をあおり、より悪化させるだけだ」
──とニュージャージー州のコリー・ブッカー上院議員は述べた。
見た目はややこしいですが、結局この文も SVCのシンプル構造。
主語=「大統領がこれを行うこと」
述語=「is」
補語=「only going to incite …」
👉 骨格をつかめば、長くてもスッと意味が通るのです。
次はいよいよまとめに向かって、「SVOC+修飾語」というシンプルルールを再確認していきましょう。
英文ニュースサイトの活用はこちらの記事が参考になります:
→週末はBBCでゆっくり精読|AIも駆使する究極の多読×精読法
まとめ|英語長文を読むなら“SVOC+修飾語”で十分

ここまで3つの英文を読み解いてきました。
短い文でも、長いBBC記事でも、結局は同じ結論にたどり着きます。
👉 英語長文を読むのに必要なのは、この3つだけ。
1. 品詞を見抜く力(SVOCの土台)
2. 文型の理解(SVCやSVOなど、骨格をつかむ)
3. 修飾語の見極め(どこにかかっているのかを判断する)
つまり、どんなに複雑そうに見える英文も──
「これはSVOCのどれ? そして修飾語はどこにかかってる?」
ってことを意識しながら読むだけなんです。
トビーが20年かけて迷走しながら気づいた真実。
それは、英語はシンプルに捉えるほど読める言語になる ということでした。
「トビーよ、そうは言っても難しいやろがい」って気持ち、よくわかります(笑)
実際、トビーがBBCやCNNを読めるようになったのは、英検1級やTOEIC900点を越えてからでした。
でもみなさんは、このシンプルな事実を先に知っていれば、トビーのように20年も路頭に迷う必要はありません。
そのためのヒントはこのブログにたくさん落ちています。ぜひ参考にしてみてくださいね。
このブログを書いた人:トビー
20年迷走して、ようやく“精読の壁”を超えた人です(笑)
トビーって何者?って思った方は、こちらをどうぞ(笑)
→このブログについて|20年迷走して気づいた“精読”の力とTOEIC900の壁

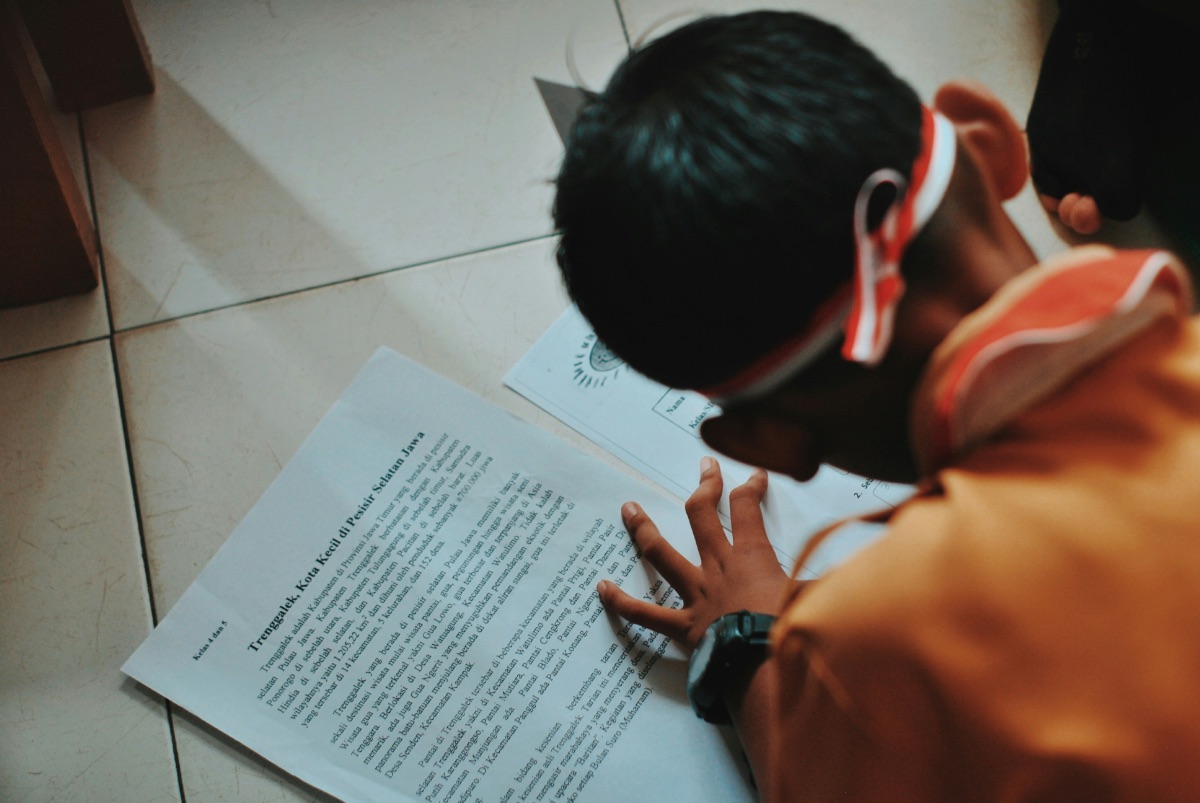

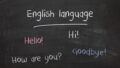

コメント